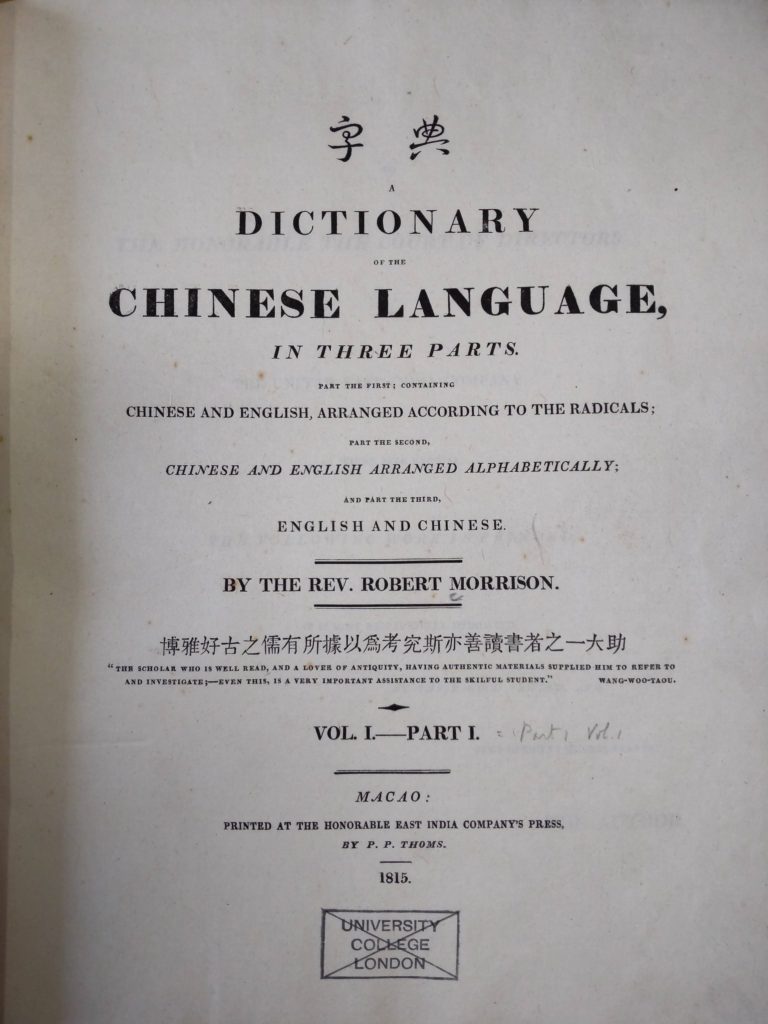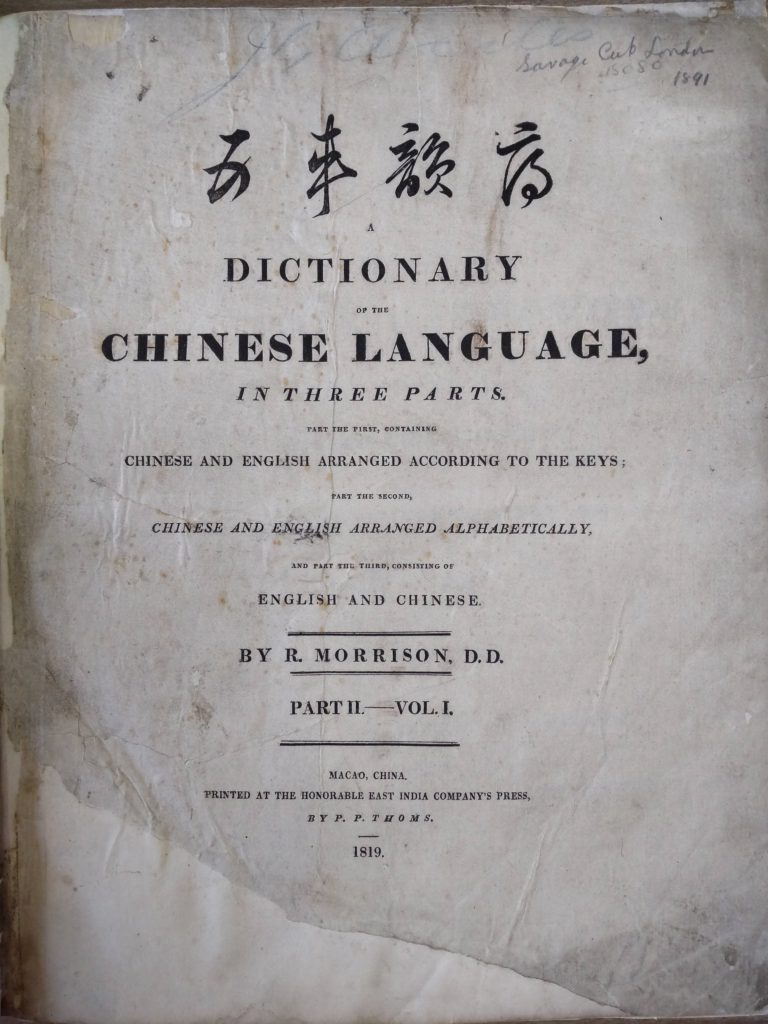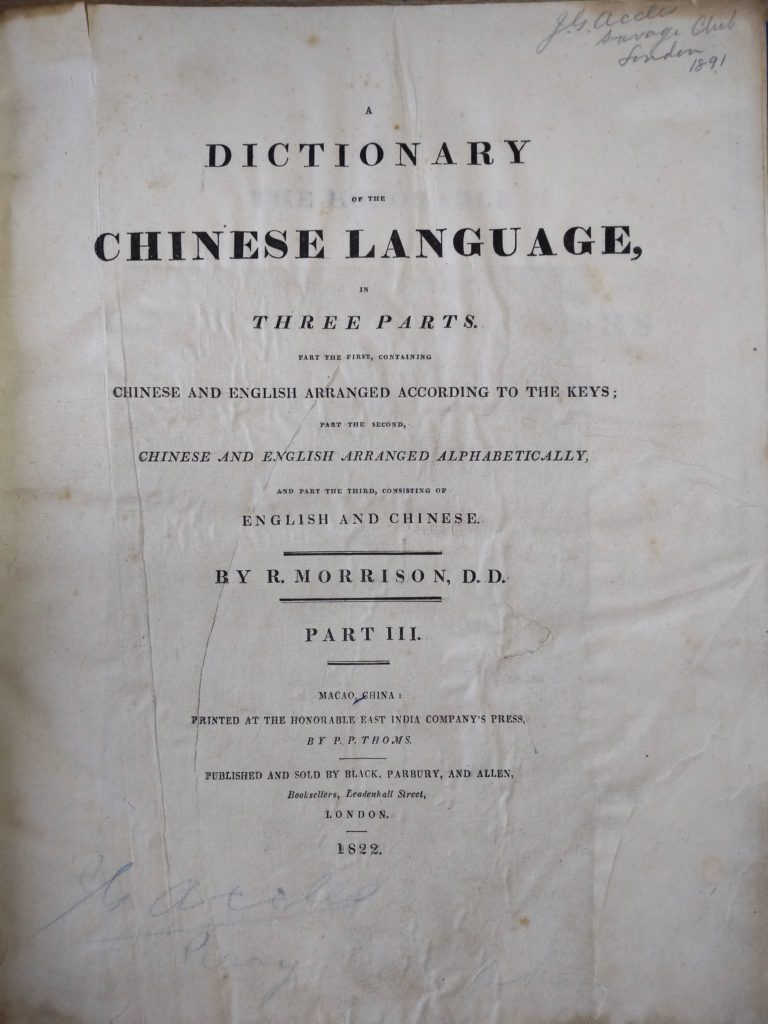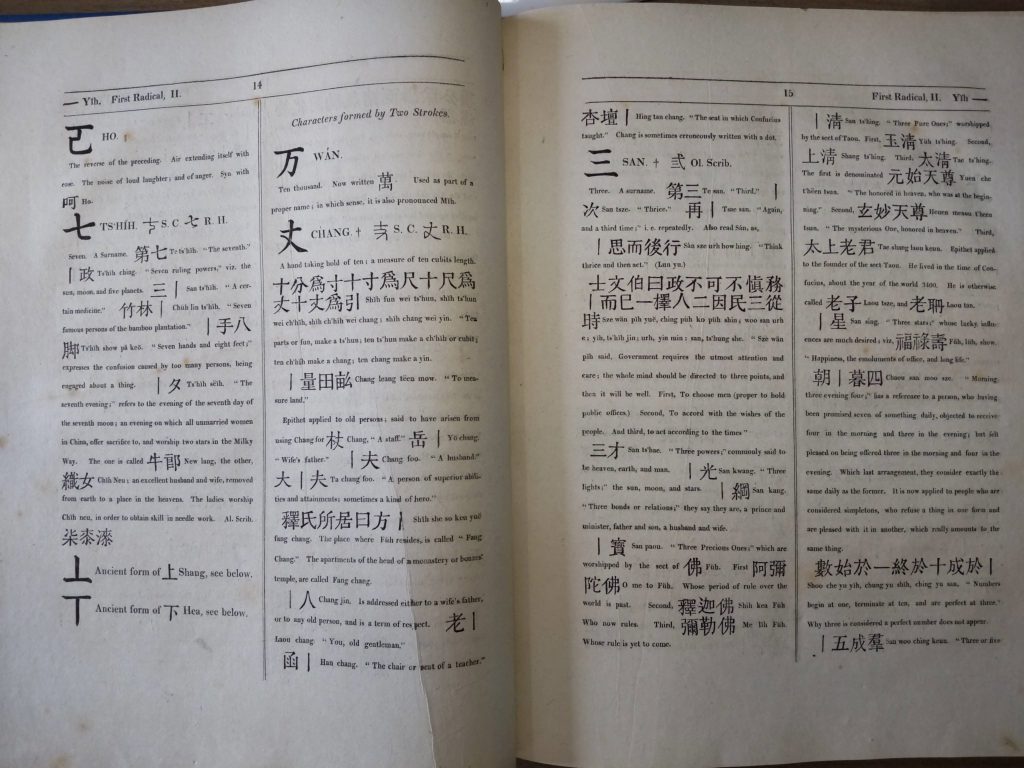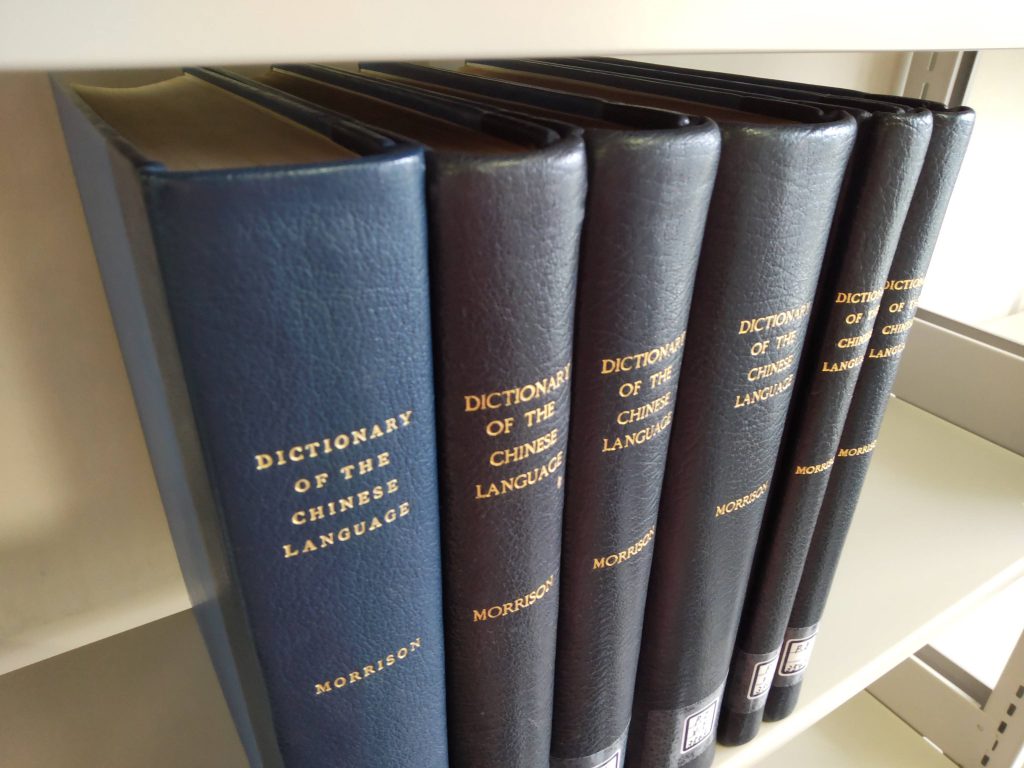第一条 本会は「上智大学国文学会」と称する。
第二条 本会は、国文学・国語学・漢文学の研究とその交流に努め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 本会は、上智大学国文学科の関係教員および卒業生、大学院生、並びに入会を希望する者で理事会の承認を得た者を以て会員とする。学生は準会員とする。
第四条 本会は毎年一回総会を開く。
第五条 本会は左記の事業を行う。
一、研究発表会の開催
二、国文学論集の刊行
三、ホームページの維持
四、その他、親睦会・講演会など本会の目的を達成するために必要な事業
第六条 本会には左記の役員をおく。
一、会長 一名
二、理事 若干名
三、評議員 若干名
四、幹事 若干名
五、会計監査 二名
役員の任期は二か年とする。ただし、重任を妨げない。
第七条 会長は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定する。
会長は本会を代表する。
第八条 理事は左記により定める。
一、国文学科の在職者の互選
二、会長の委嘱
理事は理事会を構成し、会長を補佐して事業の立案並びに会の運営に当たる。
第九条 評議員は、会長の推薦に基づき、総会の承認を得て決定し、会長の諮問に応じて必要な事項を評議する。
第十条 幹事は会長が会員の中から委嘱し、会計・編集その他の専門の業務に当たる。
第十一条 会計監査は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定する。
第十二条 会長は必要に応じて委員会を設けることができる。
第十三条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入を以てこれにあてる。
第十四条 本会の入会金は二千円、会費は三千円(準会員は二千円)とする。
但し、卒業年次入会の場合は入会金を免除する。
第十五条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
理事会は総会において毎年度決算報告を行う。
第十六条 本会の規約改正は理事会の発議を経て、総会の承認を以て行われる。
付則 本会は事務局を、千代田区紀尾井町七番一号 上智大学国文学科事務室におく。
昭和六十年四月一日より施行
平成二年七月七日改正
平成十四年七月六日改正
平成二十四年七月七日改正
平成二十九年七月一日改正
名誉会員推薦内規
一、次の者を理事会の承認を得て、名誉会員に推薦する。
二、専任教員として上智大学で定年を迎えた者。
三、会員のうち七十歳以上の者で、次のいずれかの項目に該当する者。
(一)本会の役員に十年以上在任した者。
(二)本会の事業に多大の貢献をした者。
四、名誉会員は、会費納入の義務を免除する。
(昭和六十三年七月九日より施行)
(平成二十四年七月七日改正)
準会員取扱内規
一、単年度会員とする。(会員名簿には記載しない。)
二、国文学論集の配布をうける。
三、大会への参加が認められる。
四、論集への論文の掲載が認められる。
(但し、国文学科指導教授の推薦を必要とする。)
(平成二年七月七日より施行)
(平成二十九年七月一日改正)