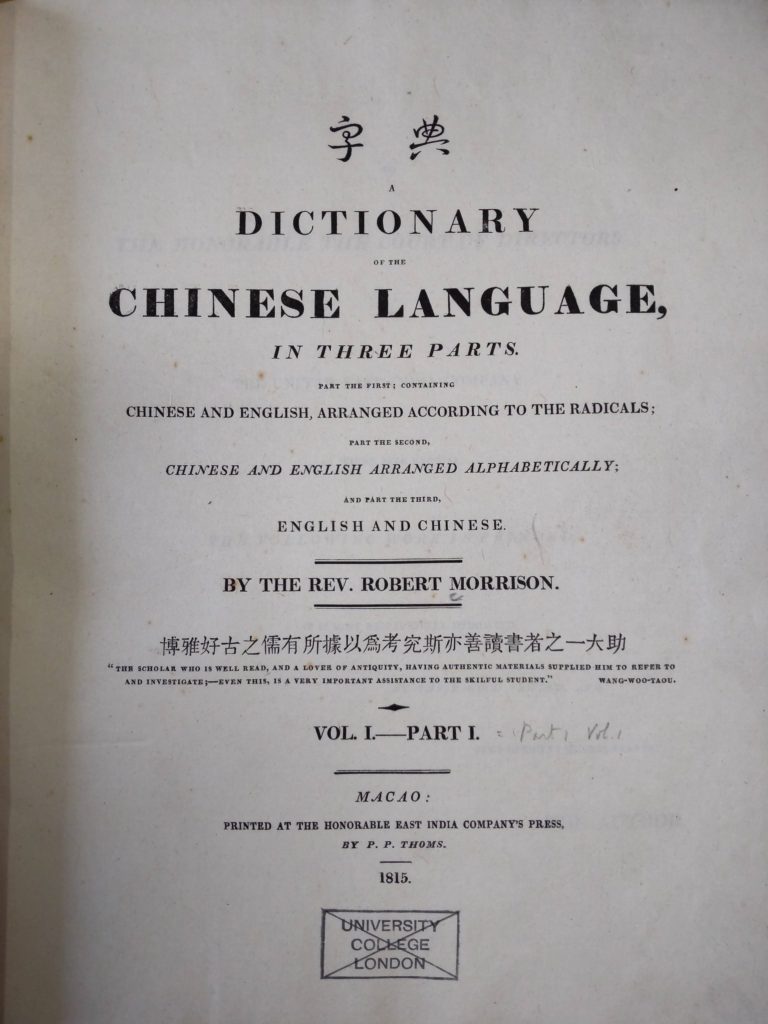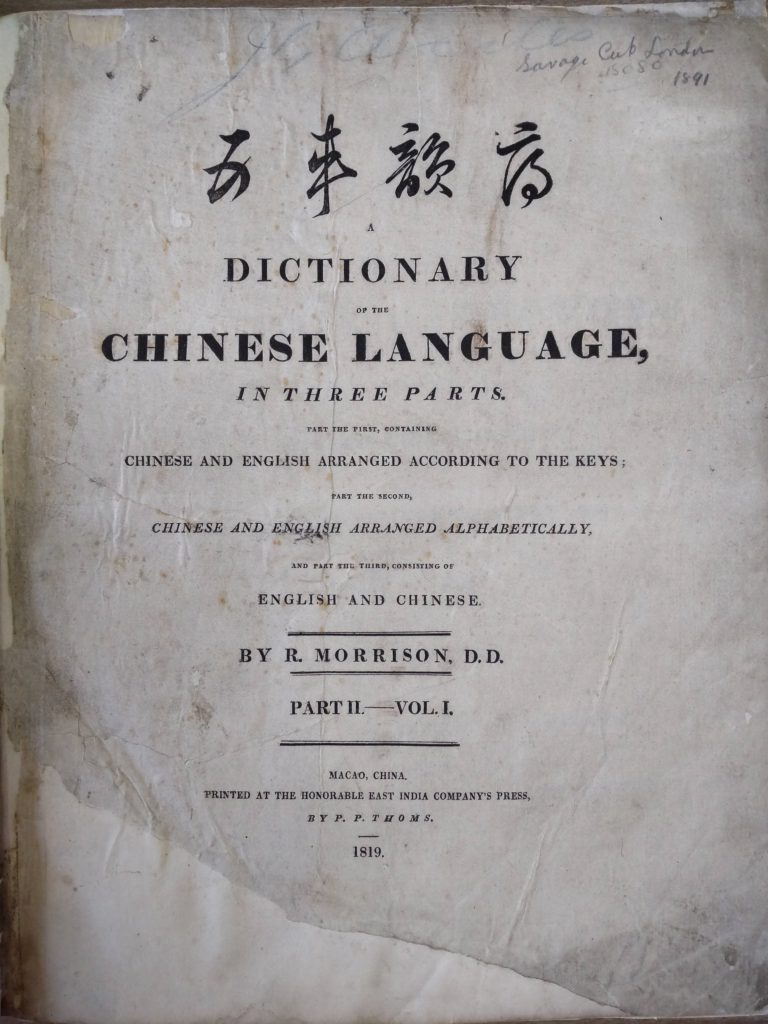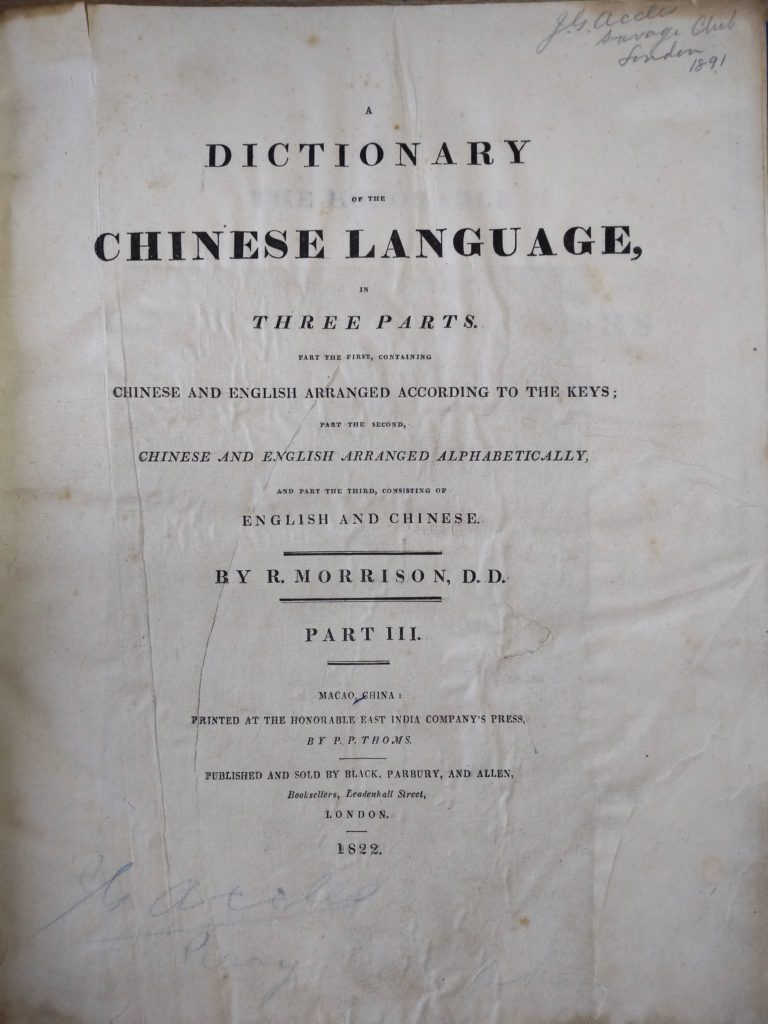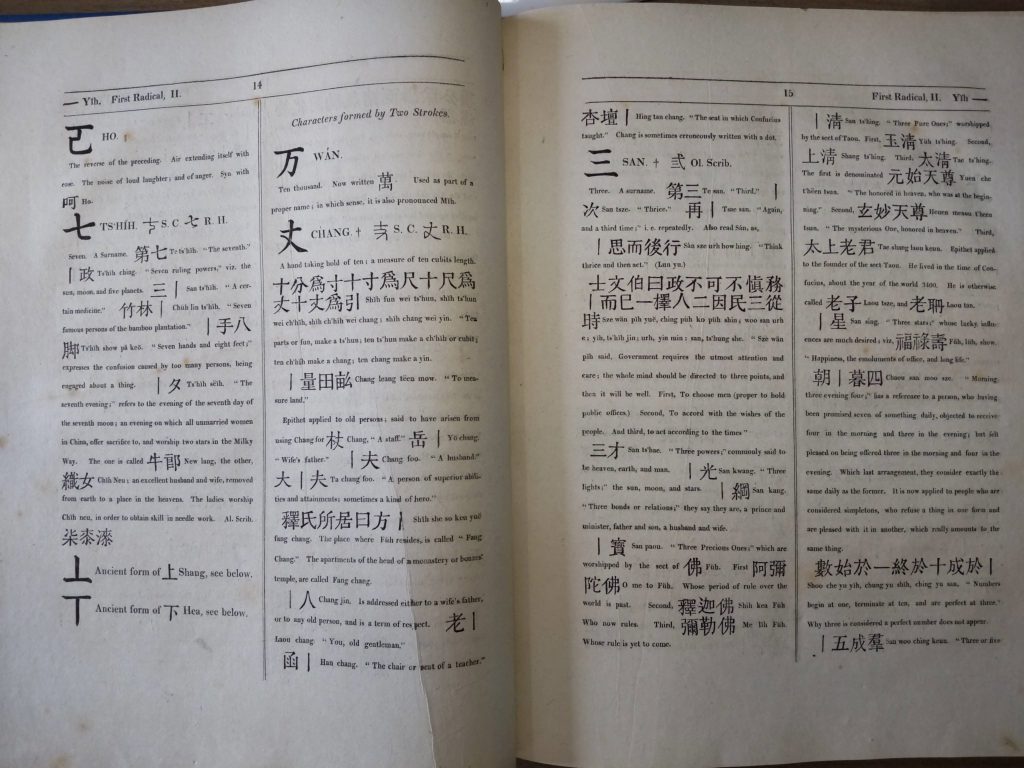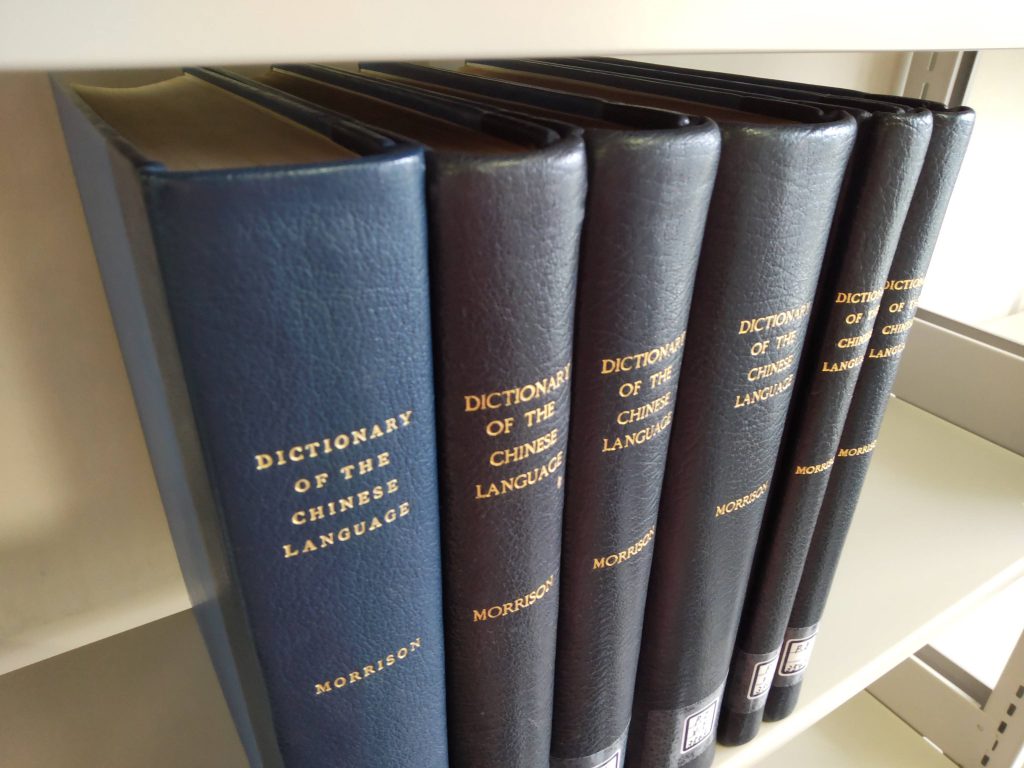研究発表要旨
唐代における詩語「王昌」の受容と李商隠詩 早坂 伊織
李商隠の「楚宮二首」其二には王昌という語が使用されている。この語は唐代に集中して見られるもので、李商隠の詩もその一群に属するといえる。ここでの王昌とは実在した特定の人物ではなく、詩人たちによって培われたイメージの集積、虚構の人物である。この王昌について調査したものでは塩見邦彦のものがあるが、塩見の調査は未だ十分ではなく、修正する余地も残されているように思える。
そこで本発表では、唐代の王昌を詠んだ詩を読むことを通し、塩見の調査を再検討する。次いで、その過程で得られた成果をもとに李商隠詩を検討し、李商隠が王昌という詩語を自らのうちにどのように取り込んだのかを考察することを通して、李商隠詩の性格の一端を示す。
今の天下は文士の天下にして
——日露戦争後の文学者像と告白小説 木村 洋
一九〇七〜〇八年頃のさまざまな新聞や雑誌の記事から、文学者が政治界などの偉人と肩を並べるような新式の偉人として社会に君臨していく様子が見えてくる。こうした文学者の偉人化は同時代の言語表現にも影響を及ぼさずにはいなかった。日露戦争後に流行する告白小説(私小説)は、「今の天下は文士の天下にして」と言われたような情報環境に支えられるかたちで、発展のきっかけをつかんでいった。そのことをふまえると、告白小説を非社会的な表現と見なす従来の理解には修正がいるだろう。文学者の生活や思想が公的な意味を帯び始めたからこそ、告白小説という、文学者自身の生活や思想を描くことをよしとするような小説を書くことが促されたからである。
座談会趣旨
教職課程科目「国語科教育法」で求めること、求められること
比留間 健一
国語の教員免許の取得に必要な「国語科教育法」の担当者による座談会を計画しました。現行のシステムでは、春学期に二人、秋学期に二人の担当者がいますが、中学・高校の免許の取得にはそのすべてを履修することが必要です。
今回は、春学期の担当者である比留間より、この授業の受講者にどんなことを求め、どんな授業をしているかをお話しし、それを糸口に他の担当者と意見を交換していく予定です。大会の開催の時点で、春学期の授業はほぼ終わっているので、今年の受講者の様子も紹介できたらと思っています。現場の教員の皆さんから「こういうことは身につけて教育実習に送り出してほしい」という声も聞かせてください。